

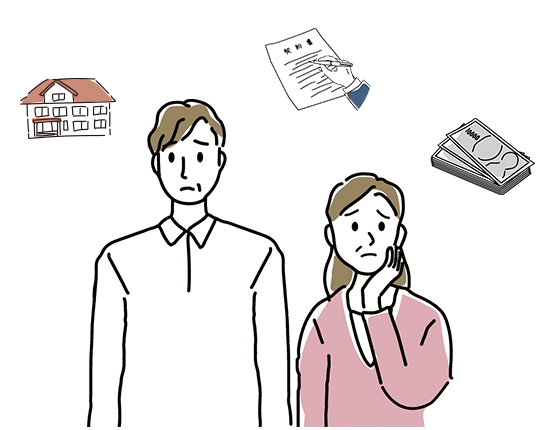
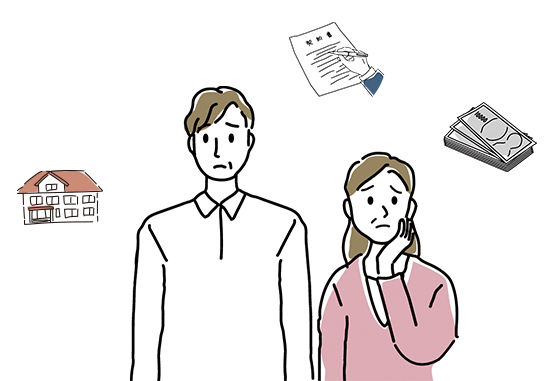
※このサイトは(一社)全国幸せ相続計画ネットワークをスポンサーとして、
Zenken株式会社が運営しています。
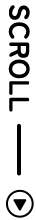

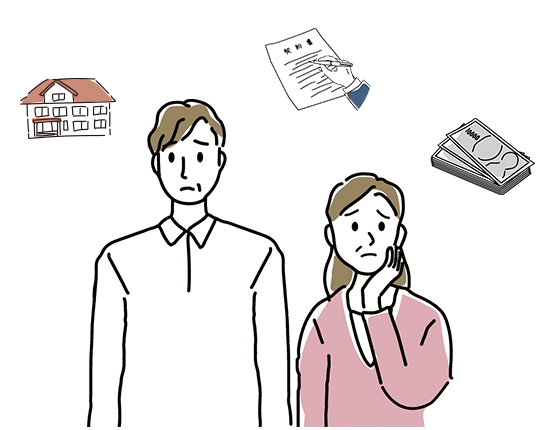
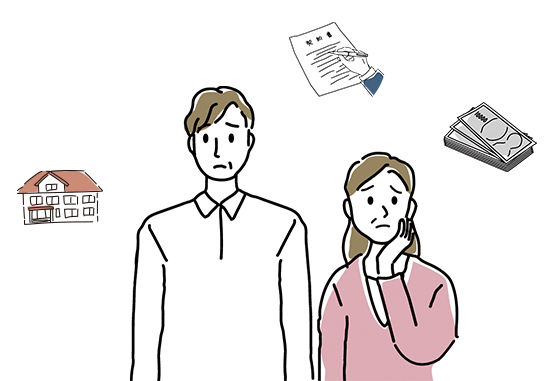
※このサイトは(一社)全国幸せ相続計画ネットワークをスポンサーとして、
Zenken株式会社が運営しています。
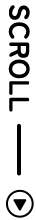

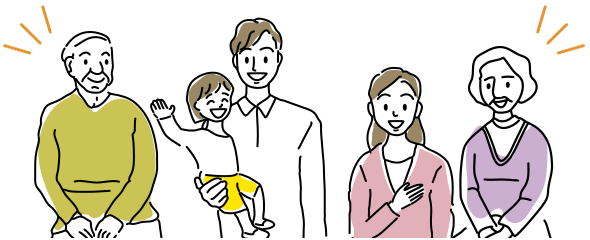
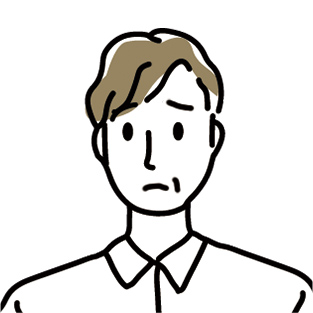


両親が75歳を迎えたり、認知症を発症した場合、不動産の売却や贈与、名義変更などを本人の意思で行うことが難しくなります。
相続対策が進まないまま固定資産税だけが発生し、土地の活用もできない状態に。家族であっても自由に動かすことはできず、成年後見制度※1という法的手続きが必要です。
ただ、申し立てから完了までには数ヶ月かかることもあり、時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。
(※1)成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分になった人の代わりに、法的な手続きをしてくれる人(成年後見人)を裁判所が選ぶ制度のことです。
(※2)参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)
相続は“ある日突然やってくる”のに、つい「その時が来たら考えよう」と先延ばしにしてしまうものです。
でも、たった一度の話し合いや少しの準備で、こうした後悔は防げたかもしれません。
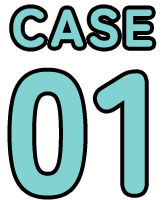
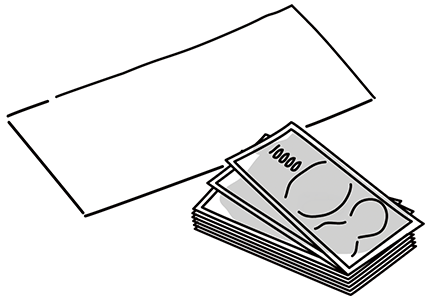
いざ相続税を支払うとき、預金がほとんどなくてすぐに払えなかった。
事前にいくらかかるのか具体的に知っておけばよかった...。
お金の負担ばかりが残り、兄弟間で責任のなすり合いにという後悔。
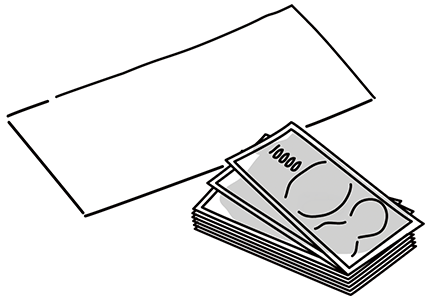
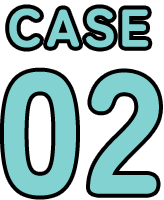
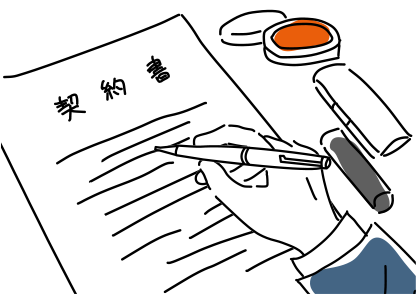
相続税は10ヶ月以内に一括払い。期日が迫っていて急いでいたから、とりあえず売れそうな不動産を売ってしまった…。
後から「なんであの土地を売ったんだ、お金になる土地だったのに」と家族内で責められ、わだかまりだけが残ったという後悔。
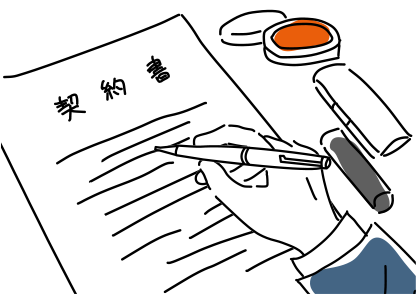
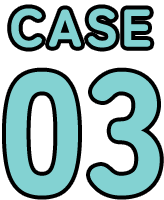
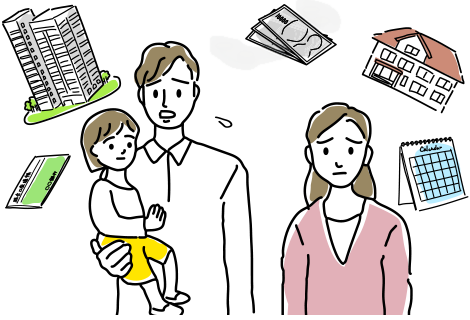
空室、修繕、返済…親の不動産の相続税対策として建てたマンションの管理が、自分や子どもの悩みの種になっている。
相続税の事しか考えずに進めた結果、実際にはそれほど節税効果はなく、財産を分けてみると期待したほどのメリットはなかった。
借入額が大きすぎて、子どもには多額の管理コストという重荷だけが残ってしまった…という後悔。
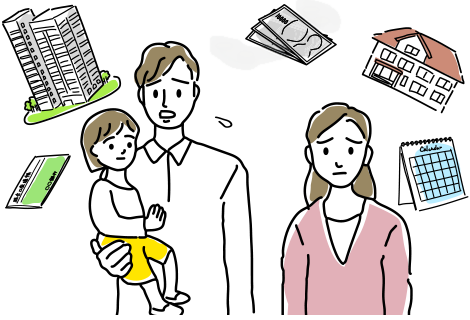
相続でもめるポイントは、子どもたちの漠然とした将来の不安からくる財産の分け方。
さらに、相続税で優良な財産が減ることで、もめ事が大きくなり、家族がバラバラになることも。
私も親の実家の相続トラブルを経験しました。その時、気づいたのは「相続対策」という言葉はよく耳にするけれど、家族をもめさせないための対策が全く不足しているという現実。
親が元気な今、家族みんなが幸せになるための対策をしっかり行うことが重要なのです。
※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)
「親が残してくれた不動産で、家族がもめるなんて…」そんな事態を防ぐには、“事前の準備”が何より大切です。
ここで解説する3つの対策を知っておくだけで、相続への向き合い方は大きく変わります。


「だいたいこれくらいかな」と相続税を予想していたら、思った以上に高かったケースは珍しくありません。
特に、アパート、更地、駐車場など収益性・流動性が⾼い価値のある資産を⼿放さざるを得ないこともあります。
相続税の納税資⾦を不動産売却で⽤意するには時間がかかるため、早めに税額を把握し、どの財産をどう活⽤するかを⾒極めておくことが重要です。


人が住まない空き家や活用しづらい土地などの負担になる不動産は「売れにくい・収入を生まない」ため、「誰が引き継ぐか」でもめやすいのが現実です。
対策は、借地権者(住んでいる⼈)に買い取ってもらうこと。現⾦化することで、相続税の納税資⾦や他の物件の修繕費にあてることが可能になり、価値ある財産に組み替えることができます。


残せる財産の総額や使える現金の見通しが不明確なまま相続を迎えると、子や孫の将来かかるお金が足りないなどの支障が出てしまうことも。
「不動産をどう分けるか」だけでなく、「売却後の家族のライフプランまで考える」ことが⼤切です。
⼦や孫の教育資⾦などの必要資⾦を⾒越し、どう組み替えて運⽤していくのかを検討することで家族へ安⼼を残すことができます。
家族信託は、生前に不動産や資産の管理権を家族に託せるしくみで、判断能力が低下してもスムーズに管理でき、納税資金の準備も前もって行えます。
ただし、信託内容が調査や資産分析に基づいていなければ、不公平感やトラブルの原因に。家族信託と同様に、遺言書も内容がすべて。
客観的なデータとともに「親の想い」を記した付言を添えることで、感情的なもめ事の防止にもつながります。
※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)
「誰に相談すればいいのか」で迷う方は少なくありません。
実は、財産分割アドバイザー・相続コンサル・税理士など、相談先によって対応範囲や立場が異なります。
|
財産分割
アドバイザー |
相続専門
コンサル |
税理士
|
不動産
|
司法書士
|
銀行・保険
|
弁護士
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
財産分割
計画 |
|
|
※税務上 |
|
|
|
※調停 |
|
相続税
|
※シミュレーション |
※法定相続分 |
|
|
|
※法定相続分 |
|
|
老後資金
計画 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遺言書
家族信託 |
|
|
|
|
|
|
|
|
不動産の
取引 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財産分割
アドバイザー |
相続専門
コンサル |
税理士
|
不動産
|
司法書士
|
銀行・保険
|
弁護士
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
税務申告
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不動産登記
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不動産の
取引 |
|
|
|
|
|
|
|


相続の相談先は司法書士、税理士、不動産会社など多岐にわたりますが、それぞれ対応できる範囲が異なります。
違いを把握しないまま動き始めると、「ここでは対応できません」と言われ、複数の窓口をたらい回しにされることも。
効率的かつ的確なサポートを受けるには、最初に専門家ごとの役割を理解しておくことが大切です。



たとえば金融・不動産・保険会社などは自社商品を前提とした提案が多く、弁護士も相談先によっては相続に詳しいとは限りません。
相談先によっては、思ったサポートが受けられず時間や手間がかかることも。
相続全体を俯瞰し、必要に応じて各専門家と連携できる財産分割アドバイザーを活用することが、中立的かつ早期解決につながります。

一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワークは、保険やアパート建築などの販売商品を持たず、中立的な立場で相続を支援する専門コンサルティング企業です。
司法書士・税理士・弁護士のほか、金融・不動産など各分野の専門家が連携し、土地の買取相談にも対応。
社会に必要とされる仕組みであることを証明する特許※を取得した「幸せ相続計画」に基づき、ご家族三代の幸せに寄り添いながら未来につながる相続対策を実現します。
※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)
対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府・京都府・山口県・北九州市・熊本県・沖縄県
上記エリア外でも、ご相談内容に応じて柔軟に対応可能です。
ここでは、「親の不動産はいらない」と考える人に向けて、手放したあと後悔しないために、「相続放棄」や「売却」について知っておくべきポイントをまとめました。
親の不動産を相続しても、土地や建物の維持管理コストで収支がマイナスになる場合は相続放棄することができます。
相続放棄の条件や手続き、相続放棄をする上で注意すべきポイントについてまとめました。
さまざまな理由により、親の不動産を売却するケースがあります。
親の不動産を売却する前に確認しておくべき内容と、売却手続きの流れ、相続トラブルを未然に防ぐための留意点もまとめました。
当メディアはZenken株式会社の「もめナビ」編集チームが、親の不動産についてリサーチし、制作したサイト。
親の不動産でもめずに家族みんなが幸せに暮らせるように、一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワークに取材協力いただきました。